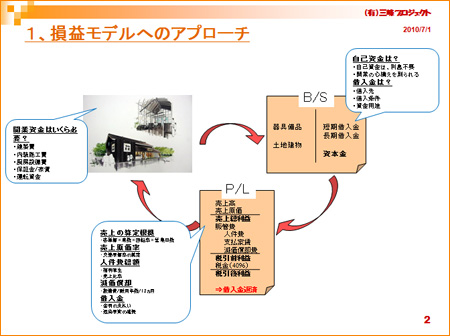新規開店、開業
◆新規開業、新規開店をお考えの方に、開店プランの基本的な考え方をご説明します。
上図は、初期投資(先行投資、設備投資)を、どのように回収するかを示しています。
結論から申し上げると、
- 初期投資は減価償却費となって「月次損益に跳ね返る」。
また、資金調達の内、借入金は支払利息となって「月次損益に跳ね返る」。
↓ - 結論として、新規開業を成功させるには、
- 初期投資を出来るだけ抑えて、
- 自己資金の範囲で出来る計画を作る
と言うことになります。
少し詳細にご説明しましょう。
◆まずは、初期投資(先行投資、設備投資)に関してご説明します。
飲食店開業における代表的な初期投資(先行投資、設備投資)としては、
- 建築費
- 内装施工費
- 厨房設備費
- 保証金/家賃
- 運転資金
などがあります。
これらの内、簡単に言えば、建物や設備に掛かった金額(設備資金)は「資産」として計上され、ある定められた条件に従って、その価値が減っていく分を徐々に経費計上していきます。これを「減価償却」と言います。
(減価償却について、詳しく知りたい方は別途お問い合わせください)
そして、この減価償却は費用ですから、月々の売上から差し引かれて利益計算をする訳です。
ここまでが、第一ステップ!
ついて来れてますか?
しかし、皆さまの中で「減価償却の領収書」って見た事ありますか?
そうなんです、減価償却って支払いを伴わないんです・・・。
難しくなってきましたね・・・?!
つまり、支払いは「初期投資」で済んでいて、それを一旦「資産」に棚上げしておいたものを、年に一回の決算処理で価値が下がった分を費用化していくんです。平たく言えば(かなり平たく言えば)、先行投資を分割払い(支払いは初期に一括払い)しているような感覚です。
こんなことは何となく分かれば結構です。
大事なことは、
- 初期投資(先行投資、設備投資)は、減価償却として月次損益に影響するから、少ないほうがイイ
と言うことがご理解いただければ結構です。
◆適正な初期投資(先行投資、設備投資)の規模とは?
- じゃあ、いくらぐらいまでを、初期投資(先行投資、設備投資)として使えばいいの?
という質問が聞こえてきそうですね。
簡単な計算式でお答えするならば、
- 先行投資額 = 見込売上/月 × 5~10% × 12ヶ月 × 5~10年
と言うことになります。
例として、「店舗面積30坪 × 10万円/月坪売上 = 300万円/月商」というお店で考えてみますと、
- 安全な先行投資額 = 300万円 × 5% × 12ヶ月 × 5年 = 900万円 = 月商の3ケ月分
- リスキーな先行投資額 = 300万円 × 10% × 12ヶ月 × 10年 = 3,600万円 = 年商分
「900万円 → 3,600万円、なんて開きがあり過ぎるじゃないか・・・! とお叱りの言葉を頂きそうですが、これは、やはりケース・バイ・ケースで対応せざるを得ない部分です。
つまり、
- 10年間修業をしてきて、コツコツと貯めてきた貯金と親からの借金で出店したい・・・
- 20年間飲食店をやってきて、今回、満を持して2号店を出店したい。利益留保が潤沢なので、ほとんど自己資金で賄える
これらによって、対応は様々だからです。
また、見方を変えると、安全な投資額の場合、
- 900万円 ÷ 30坪 = 30万円/坪建築費
となります。
つまり、「坪当たり30万円で店舗を仕上げろ!」ということです。
この考え方にも、賛否両論あると思います。
でも、僕(鈴木秀樹)は、敢えて、このように指導しています。
結論として、「居抜の物件」しか選択肢がなくなってしまいます。
それは、
- 内装設備で集客するのは、大手のやり方
- 商売は続けてこそ意味がある
と思っているからです。
お金を掛けた内装でも清掃が行き届いてなければ、お客様はリピートしてくれません。
逆に、質素な内装でも、清掃が行き届き、磨き上げたような店内であればお客様は必ずリピートしてくれます。
◆初期投資(先行投資、設備投資)に関して、結論!
- 初期投資(先行投資、設備投資)は、出来るだけ低く抑えることで、月の収支の黒字化を図る
- 個人で開業する場合、初期投資(先行投資、設備投資)は、月商の3ヶ月を目安に検討するべき
◆今日は、開業時の資金調達について書いていきます。
前述の初期投資(先行投資、設備投資)に従って、開業プランを進めていくと、次なる課題は「資金調達」です。
ここでも、結論先だし・・・!
- 最低でも、初期投資の1/2は自己資金で賄う
「全額自己資金」と言うのが理想なのは言うまでもありませんが、働きながら(修業をしながら)、そこまで貯めることはほぼ不可能ですよね。
そうなると、必然的に借入を起こさなくてはなりません。
その際に、借入先である銀行では、
- 1/2以上は、自己資金で賄っている
と言うことが必須条件となります。
なぜか?
◆開業時の自己資金は、開業準備の心構えを見られるのです。
開業資金の1/2以上を、自己資金で賄っていることの意味合いとしては、
- それだけ、準備期間を持って準備してきた
- 覚悟を決めて、この開業に今までの人生を掛けている
という心構えを示しているということなのです。
◆さらに、自己資金比率が高いことにより「月次損益」を楽にします。
借りたお金は返さなければなりません・・・、しかも、利息をつけて・・・。
具体例で見てみましょう。
例えば、先行投資総額:1,000万円(見込売上300万円/月)だったとします。
(借入金利3%、借入期間5年とします。元利均等とか、複雑なお話は置いておきましょう)
- 自己資金1/2とすると、借入金は5百万円。
初年度の利払いは「1万1250円」となり、「売上比0.375%」 - 全額借入とすると、借入金は1千万円。
初年度利払いは「2万2500円」となり、「売上比0.75%」
投資総額から比べると、大して差がないじゃないか・・、と感じるかもしれませんが、分かりやすいように人件費に換算すれば、
- 時給@¥800として、約14時間分
↓
ランチタイム(11~14時)のパートさんとして「約5日分」
自己資金を半分用意できていれば、
- 1週間分のランチタイムのパートさんの人件費が捻出出来ていた
という訳です。
大きいですよねぇ・・・!
◆当然、元金も返済しなくてはなりません・・・。
利払いだけではなく、元金も返済していかなくてはなりません・・・。
先程の例で言えば、
- 自己資金1/2(借入金5百万円)の場合は、月々の返済額は約「8万3千円」
- 全額借入(借入金1千万円)の場合は、月々の返済額は約「16万6千円」
チョット複雑になりますが、借入金の返済原資は、
- 返済原資 = 利益 × 0.6 + 減価償却費(前述)
となります。
先ほどの投資計画に従って、減価償却期間を7年(残存0円、定額法)と仮定すると、
- 減価償却費 = 1千万円 ÷ 7年 ÷ 12ヶ月 = 11.9万円(売上比4.0%)
となりますので、上記の例に当てはめれば、必要利益は、
- 自己資金1/2の場合 =(8万3千円-11.9万円)= 減価償却で返済額を賄える
- 全額借入の場合 =(16.6万円-11.9万円)÷ 0.6 = 7万8千円(売上比2.6%)
ここで大事なことは、金額や売上比率ではなくて(それも大事なのですが・・)、
- 自己資金を1/2用意していれば、「赤字」でも返済に困らない
と言うことなんです。
(厳密に言えば、現金出納レベルではやはり「利益」が出ている必要があるのですが・・・)
◆根拠はいろいろありますが、結論としては・・・、
上記の通り、数字上で自己資金の重要性を説明してきましたが、ちょっと難しい・・、かもしれませんね。
結論としては、
- 開業計画では、自己資金1/2以上を用意する
これが、必要だということです。
- そんな貯金ないし、親からの借金も出来ないよ・・・
そんな方がいらっしゃるかもしれません。
即答します!
- 投資計画を縮小して、予算の範囲内に計画を修正して下さい
- または、貯金が貯まるまで、待って下さい
僕(鈴木秀樹)は、思います。
貯金が貯まるまで待つことも、開業計画の一環です。すでに、そこから開業計画がスタートしている訳です。
例えば、銀行さんに借入に行った時に、
- 3年前に開業計画を作成した時に、自己資金が足りなかったために、投資計画を若干縮小して、さらに3年掛けて100万円の貯金をし、「総額5百万円で総投資額の1/2の自己資金」を用意しました。
と言うお話をされたら、グッと借入の可能性は高まりますよね。
言わずもがな、「事業の安全性」も高まっています。
是非、こんな開業計画を作って頂きたいと願っています・・・。

中小飲食店の専門コンサルタント
代表取締役社長
鈴木秀樹
私も、かつては飲食店で「300時間/月」の働きがいのある(?)現場で、頑張っていました。飲食業に携わるすべての人々が、もっともっと幸せになれるようにお手伝いをさせて頂きます。
~リンク集~
〔飲食店コンサルのお仲間〕
〔中小企業診断士のお仲間〕
〔Movable Typeのお仲間〕
〔クライアント企業様〕
〔(有)三峰プロジェクトのHP〕